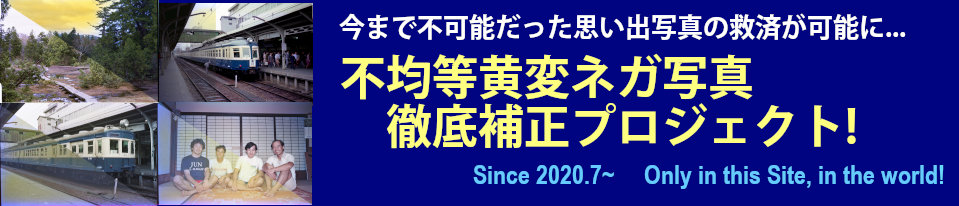目次: ART を使った不均等黄変ネガフィルム画像の補正テクニック
(1) チャンネル再構成で黄色味を消す (本ページ)
(8) 追加補正: 狭まった B チャンネルのダイナミックレンジを復原する
----------------
先日、自作の ART 用 CTL スクリプト、チャンネル再構成 スクリプトをバージョンアップしました。このバージョンアップの目的は、不均等黄変を起こしたネガフィルム画像の修正対応能力を高めることです。
これにより、ART でもより広い範囲の不均等黄変画像の画像補正が可能になっていますが、それに合わせて、今後何回かに分けて ART を使った不均等黄変画像の画像補正テクニックについて解説していきます。
なお、ART それ自体の紹介や、インストール方法については、下記の ART 情報インデックスページから記事を探してお読みください。
さらに、拙作の ART 用 CTL スクリプトがインストールされていることを前提に説明していきますので、まず準備としては以下の拙作 CTL スクリプトを ART にインストールしておいてください。
なお、ImageJ + GIMP に拙作の ImageJ 対応 B チャンネル再建法ツールを使った黄変画像の補正は、補正手続きが半自動化されています。最終的に、マスク編集や補正に使うレイヤーの選択などはユーザがマニュアルで行うようになっていますが、手続きが半自動化されているために、基本的に補正ワークフローをあまり考えなくて済みます。
しかし、ART のみを使った黄変画像の補正は、ツールは提供しておりますが、手続きが半自動化されているわけではないので、自分が何をやっているのか、ちゃんと把握しながらやっていないと、途中で訳がわからなくなる可能性があります。また、RGB三原色の原理や原色ー補色の関係などちゃんと理解していることが前提となります。
また CTL スクリプトの仕様からピクセル単位での処理しかできないため、ImageJ 対応ツールより使えるアルゴリズムが限られ、補正力はやや劣ります。
様々なソフトウェアを使い分ける必要はありませんが、難易度という点では、元画像にもよりますが、必ずしも ImageJ 等を使った補正よりも易しいとは限らない点に留意してください。とは言え、比較的単純なパターンの変色であったり or 変色の程度が軽微であったりすればこちらの方法の方が簡単です。
ImageJ を使ったツールについては以下をご覧ください。
■ 黄変した部分を補正する
では以下テクニックの説明に入ります。
まずは黄色く黄ばんだ部分の補正方法です。これには拙作のチャンネル再構成スクリプトを使う方法と相対色領域補正スクリプトを使う方法があります。チャンネル再構成は基本的にチャンネルミキシングまたは入れ替えによって黄変の除去を目指し、相対色領域補正はマスクを掛けた範囲の各色の値を直接動かすことで、黄変の除去を目指します。どちらが適切かは画像や黄変状態によりけりです。まずチャンネル再構成スクリプトを使った方法について解説します。
・チャンネル再構成スクリプトを使う
まず、チャンネル再構成スクリプトを使った方法から解説します。まずオリジナルのサンプルファイルをご覧ください。

空を中心に不均等に黄色くなっています。また、その上の画像のフチは黄変褪色も見られます。この黄変を取り除いていきます。
まず、画像を読み込んだら、カラー/トーン補正で、モードから[チャンネル再構成] を選びます。さらに、修復するチャンネルは [ブルーチャンネル] を、ミキシング方法には、[明度引上げ適用] を選択します。明度引上げ適用はチャンネルミキシングした結果オリジナルのピクセル値より高い場合のみ、新しくミキシングしたピクセル値と置き換えるというオプションです。

ブルーチャンネルを選んだだけで黄色味が薄くなり、あっさり補正できてしまいました。これはデフォルトでレッドが100%になっているためです。なお、この画像の場合黄変部分以外の場所はほぼ画像に変化がないようです (これは単なるラッキーです)。但し、周辺が青紫になっていますが、この補正については後日の記事で解説します。

一旦、元の画像に戻したい場合はブルーを100%に、他のチャンネルは 0% にします。なお個人的にはグリーンを多めにレッドを少なめにミックスし、ブルーは 0 にするぐらいが適当なように思います。
この画像の場合これで十分なようですが、もし黄変した場所以外には補正を掛けたくない場合は、相対色マスクを適用します。相対色マスクの適用から、適用したい対象色を選んでください。下の例では、Yellow を選んでいます。黄色を補正したい場合は通常 Yellow を選びますが、画像によっては Red を選んだほうがうまく黄変領域にマッチしたマスクを作れる場合もあります。これは、黄色とはそもそもRGB値的には、R, G 値が高く、B 値が低いことであるためと、経験的にはこの手のフィルム画像の黄変は、黄色味が若干赤みを帯びているケースが多いためです。

対象領域を表示したところ
さらに、上の例ではマスク: 対象色の傾きを調整しています。また、マスクの範囲が広かったり狭かったり、マスクのトーンの傾きが合わないという場合は、対象色の閾値調整や、ガンマ調整で対応します。また補正が足りないという場合はマスクの透過度で調整します。パラメータの詳細な意味については拙作スクリプトの説明ページを見てください。
これで、対象領域の表示のチェックを外すと以下のようになります。

なお、相対色マスクを掛けた時に境界付近の色が目立ってしまう場合は、マスクの [均一の透過度適用] にチェックを入れると改善する場合があります。
※どうしても色領域マスクが変色域にマッチしない場合
なお、相対色領域マスクではうまく領域指定できない場合は、ART ビルトインのパラメータ指定マスクを使ったり、エリアマスクを使ったりすることでよりうまく範囲指定できる場合があります。
下のケースは、パラメータ指定マスク (明度) とエリアマスクを組み合わせて補正を行っているケースです。

これに単純にチャンネル再構成で、明度引上げ適用を使って、B チャンネルを他のチャンネル画像で代替すると、上のケースとは異なり、十分に黄色味が取れません。

かと言ってガンマを引き上げたり、明度を引き上げたりすると、不必要な部分が青っぽくなります。
これにマスクを掛けて、さらに明度やガンマを引き上げたところ、黄変の真ん中あたりは青っぽくなるのですが、境界領域がなかなかうまく補正できず段差ができます。

このような場合、色マスクではなく、空全体を指定し、B チャンネルを入れ替えます。

空全体を指定するために、相対色マスクではなく、ART のビルトインマスクのパラメータ指定マスク (明度)、とエリアマスクを併用します (上図)。
その上で、ブルーチャンネルにレッドチャンネルを代入し、空の明るさを増すためにガンマ補正等も行っているところです。

なお、空にマゼンタが残っていますが、これはブルーチャンネルではなくグリーンチャンネルを補正するインスタンスを加えて対応します。

本ツールの色域範囲指定機能は、既存の画像処理ソフトウェアよりもはるかにきめの細かい色域範囲調整が可能ですが、それでも、変色の濃度が激しい場合など、うまく変色の範囲にマッチする色域範囲が作れない場合があります。その場合は、上のように、ART のビルトインマスクを使って一定の領域のすべてを他チャンネル画像に置き換えて、ガンマや明度を調整したほうが良いでしょう。
以下、次の記事に続きます。
------------
[関連記事]